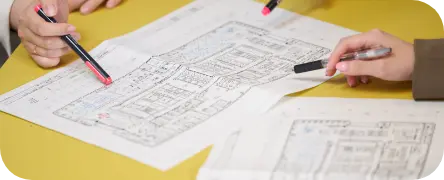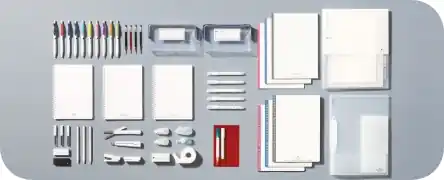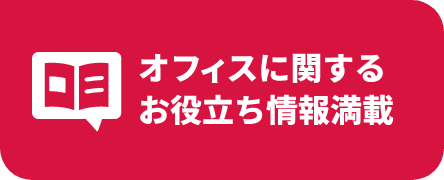従業員が働きやすいオフィスレイアウトにするためには、管理職の席次が重要です。
この記事では、企業の経営者や総務担当者に向けて、
管理職と部下がよい距離感でいられるオフィスレイアウトについて解説します。
双方の距離感が大切な理由や配置の種類、
レイアウトを決める際のポイントについても紹介するため、参考にしてください。
管理職の座席配置に関するトレンド
現代の職場環境において、管理職の座席配置は見直しの時期を迎えています。従来の固定席から脱却し、より柔軟で効率的な配置を検討する傾向にあります。
フリーアドレスの普及
フリーアドレス制度の導入企業では、管理職を含む全従業員が固定席を持たない働き方が主流となり、結果として従来の役職者固定席を設けるケースは減少しています。管理職は、コミュニケーションを重視し、必要に応じて最適な場所を選択できる、柔軟な座席選択を実現しています。
コミュニケーション重視の配置
現代の管理職には、部下との距離を縮め、オープンなコミュニケーションを促進することが期待されています。そのため、従来のような権威的な独立した管理職席ではなく、チームメンバーと同じフロアで働き、気軽に相談や報告ができる環境づくりが重視されています。

機密情報への対応
機密性の高い情報を扱う際は、専用の集中ブースや個室会議室に移動して作業を行うスタイルが定着しています。これにより、日常的にはオープンな環境で働きながら、必要に応じてセキュリティを確保できる柔軟な働き方が実現されています。

管理職の座席配置がオフィスレイアウトで重要な理由
オフィスのレイアウトでは、管理職と部下の座席の位置関係に注意する必要があります。ここでは、その理由について解説します。
部下は管理職が近いとプレッシャーになる
管理職は、部下との座席が近いと部下の様子を把握しやすくなります。一方で、部下は監視されているように感じ、プレッシャーとなることもあります。このような場合は、部下との適切な距離感を意識した座席選びが求められます。
距離感があるとコミュニケーションが取りにくい
管理職と部下の座席が遠すぎると、コミュニケーションが取りにくくなり、業務に支障がでます。管理職は部下が行っている業務を把握しにくく、部下は管理職に声をかけにくいため、相談もしづらくなるでしょう。座席の距離感が影響して、部下が管理職に苦手意識を持つ恐れもあります。
管理職には機密情報の取り扱いがある
管理職には、一般職にはない業務や権限があります。例えば、人事情報や経営戦略情報の取り扱い、人事権・決裁権などの権限です。部下との距離が近すぎると、機密情報が漏洩する危険性も高まります。適度な距離を保つことが、情報漏洩の防止につながります。また視界を遮らない高さのデスクトップパネルを設置することもおすすめです。

オフィスレイアウトの種類
オフィスレイアウトには、どのような種類があるのでしょうか。ここでは、5つのレイアウトを紹介します。
対向型(島型)
対向型は、デスクが向かい合った配置で、オフィスレイアウトの一般的なパターンです。対向型のメリットは、最小スペースでも配置ができることです。部門内でのコミュニケーションが取りやすくなるメリットがあります。一方で他の部門との連携がしづらいデメリットがあります。

並列型(同向型)
並列型は、学校のようにデスクが一方向に並んだレイアウトで、コールセンターや保険・銀行の窓口に適しています。前の座席にいる人と視線が合わないため、個々の仕事に集中できるだけでなく、機密情報やプライバシーが守られます。しかし、周りとのコミュニケーションが取りにくく、スペース効率が悪いことがデメリットです。

背面型
背面型は、デスクを背中合わせで配置します。振り向くと、まわりの従業員とコミュニケーションが取りやすく、チームとして仕事がしやすくなります。また、業務に集中しやすく、無駄なスペースが少ないこともメリットです。デメリットは、パーティションなどで仕切られるため、オフィスの様子が把握しにくくなることです。

フリーアドレス型
フリーアドレス型は、従業員の固定席を設けずに、働く席を自由に選べるレイアウトです。コミュニケーションが取りやすいため、他部署とのコラボレーションが促進されます。また、固定席をなくすことで生まれた余剰スペースを使い、リフレッシュコーナーや個人ブースなどを作ることもおすすめです。但し、従業員の居場所が分かりにくいデメリットもあるため、ICTツールや運用ルールの導入もあわせて検討しましょう。

管理職の座席配置で働きやすいオフィスレイアウトにするポイント
従業員の働きやすさは、管理職の座席配置により変化します。ここでは、働きやすいオフィスレイアウトにするポイントを解説します。
上座・下座にこだわらない
働きやすくするためには、日本の伝統的な席次マナーの上座・下座にこだわるのをやめましょう。上座は入口から一番遠い場所を指し、多くのオフィスでは窓際が該当します。管理職を窓際に配置すると、部下は管理職の視線がプレッシャーになり、働きにくくなります。マナーは大切ですが、働きやすさを求める際には、こだわる必要はありません。
管理職と部下の座席に適切な距離を空ける
管理職と部下の座席は、適切な距離を空けることが大切です。部下は管理職の座席が近いと視線が気になり、仕事に支障が出る可能性が高まるでしょう。一方で離れすぎてもコミュニケーションが取りにくくなります。1人あたりののオフィス面積の平均は会議室や受付エリアを含め10㎡程度(3坪)です。10㎡程度のスペースがあると、動線や作業場所を確保しやすく、業務効率が上がり生産性の向上が期待できます。
※参考:事務所衛生基準規則 第二章 事務室の環境管理(第二条ー第十二条) 安全衛生センター
管理職の座席をオフィスの中心に配置する
管理職が部下の様子をしっかり見渡したい場合には、オフィスの中心に座席を置くのもよいでしょう。管理職を中心にして、周りに部下の座席を配置すると、部下同士の会話が自然と耳に入りやすくなります。また、双方にコミュニケーションが取りやすくなるため、業務効率の向上も期待できます。部下は、背後から管理職に監視されるストレスから解放されて、より業務に集中しやすくなるでしょう。
窓側から出入口近くに配置する
管理職の座席は、窓側から出入り口近辺に移動するのもおすすめです。オフィスの出入口は、従業員が頻繁に通るため、部下とのコミュニケーションの促進につながります。ただし、人通りの多い出入り口近辺は、ディスプレイの覗き見や書類の紛失など、情報セキュリティ上のリスクも高まるため、機密情報の管理には特に注意が必要です。
ラウンド型やスタンディング型のデスクを設置する
管理職と部下が、報告や意見を出しあうミーティングの場には、リビングテイストの家具を設置すると、雰囲気も柔らかくなり、相談しやすくなるでしょう。また、人が集まる場所にもなりコミュニケーションの活性化が期待できます。他にも、立って会話ができるスタンディング型のデスクもおすすめです。会議室に導入すると、立ったまま会話をすることで、自由な姿勢や動きが取れて、部下の緊張感をほぐす効果が期待できます。

パーティションを活用する
単独業務が多い場合は、それぞれの座席にパーティションを活用すると、部下は管理職の視線を気にせずに業務に集中できます。一方、パーティションを設置したことで、管理職が部下の状況を把握しにくくなる、コミュニケーションが取りにくくなるといったデメリットもあるため、使い方には注意してください。パーティションを設置する際には、視線が気になりやすい対向型(島型)や背面型などの座席レイアウトに活用することをおすすめします。
業種によりベストな管理職の座席配置やオフィスレイアウトは異なる
管理職の座席やオフィスレイアウトは、業務内容や職種に合わせて決めましょう。運用しやすいレイアウトは、業種や職種により異なります。従業員に合わないオフィスレイアウトでは、業務効率が低下する恐れもあります。
デスクワークが中心の職種
デスクワークが中心となり、一般的に書類量が多い総務や開発職、経理や会計などは固定席にすると業務効率が上がりやすいでしょう。デスクを配置する際には、対向型(島型)や背面型などが向いています。固定席のオフィスでは、別途ミーティングスペースを設けると、コミュニケーションが取りやすくなります。
在籍率に変動のある職種
離席が多い営業職や、集中した環境が必要なクリエイティブ系など、企業内で職種による在籍率に変動がある場合は、フリーアドレス型やABWの導入がおすすめです。フリーアドレス型は、固定席を設けずにオフィス内で自由に座席が選べます。ABWは、仕事内容に合わせて自分が働きやすいと思う場所で働くスタイルで、オフィス以外の自宅やカフェなども働く場所になります。フリーアドレス型やABWの導入は、固定席の減少や廃止になり、オフィスの省スペース化につながるでしょう。
管理職のデスクレイアウト事例
管理職のデスクレイアウト事例をご紹介します。
固定席とフリーアドレスのいいとこどりのデスクレイアウト
西川計測株式会社九州支社様は、オフィスリニューアルに伴いフリーアドレスを導入されました。モニター付きのハイスペックなデスク席を中心に、個人でも多人数でのプロジェクトワークなどにも利用できるビッグテーブルやカフェカウンターなど、社員が自律的に働く場を選べる執務空間としました。また、役職者の席は、固定席とし仕事の相談や確認がスピーディに行える環境を作っています。

西川計測株式会社九州支社様のオフィス事例はこちらのページでご紹介しています。
まとめ
オフィスレイアウトでは、管理職の座席配置によって、部下の業務効率が左右されるといえます。適度な距離を保ち、双方が効率的に働けるようにレイアウトにしましょう。
コクヨマーケティングは、豊富な実績から、お客様の働き方にあった空間提案をします。オフィス移転から移転後のオフィス維持・運用まで、ワンストップでサポートするので安心です。コクヨ社員が実際に働くオフィスを体験できる「オフィス見学会」も実施していますので、レイアウトや働き方の参考にいかがでしょうか。ぜひお問合せください。
オフィス移転・改装レイアウトの課題を解決します
管理職の座席配置に関するよくある質問
- Q1: 管理職の座席配置で最も重要なポイントは何ですか?
- A1: 機密情報の保護と適度な距離感の確保が最重要です。管理職は人事情報や経営戦略を扱うため、部下との距離が近すぎると情報漏洩のリスクが高まります。一方で、コミュニケーションが取りやすい配置も必要です。適切なバランスを保つことが大切です。
- Q2: 管理職をオフィスの中心に配置するメリットは何ですか?
- A2: 部下の様子を見渡しやすく、双方のコミュニケーションが促進されます。部下同士の会話も自然と耳に入り、業務効率向上が期待できます。また、部下は背後からの監視感から解放され、業務に集中しやすくなります。中心配置により開放的な環境が生まれます。
- Q3: 従来の上座・下座の概念は管理職配置に必要ですか?
- A3: 働きやすさを重視する場合、従来の席次マナーにこだわる必要はありません。上座である窓際に管理職を配置すると、部下が視線のプレッシャーを感じて働きにくくなります。マナーよりも実用性と働きやすさを優先した配置を検討することをおすすめします。
- Q4: パーティションを活用する際の注意点はありますか?
- A4: 部下の集中力向上には効果的ですが、管理職が部下の状況を把握しにくくなる、コミュニケーションが取りにくくなるデメリットがあります。対向型や背面型などの座席レイアウトで視線が気になる場合に活用し、使い方には注意が必要です。
- Q5: 職種によって最適な管理職配置は変わりますか?
- A5: はい、業務内容や職種により最適な配置は異なります。デスクワーク中心の総務・経理は固定席の対向型や背面型が適し、営業職やクリエイティブ系など在籍率に変動がある職種はフリーアドレス型やABWの導入がおすすめです。業種特性を考慮した選択が重要です。